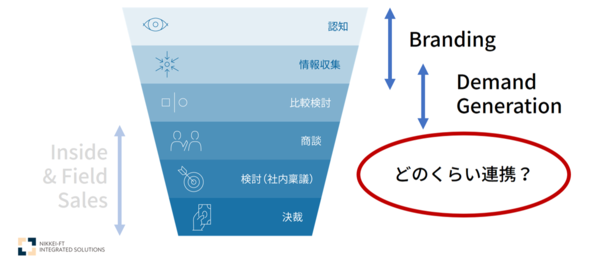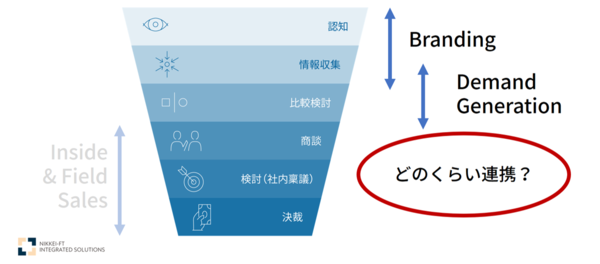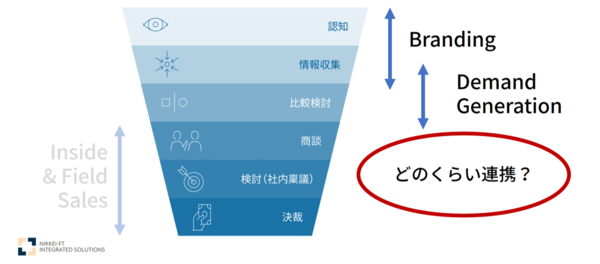

左から電通 梅木氏、セールスフォース・ドットコム 田中氏、シンフォニーマーケティング 庭山氏。モデレーター:日本経済新聞社 國友
日本経済新聞社とFinancial Timesは2019年のAdvertising Week Asiaで「結果に貢献するBtoBマーケティングを考える」をテーマにトークセッションを実施した。本稿ではデマンドジェネレーションについて、「商談創出のためのマーケティング手法とKPI」を3人のプロフェッショナルが論じた際の質疑応答部分をまとめた。
チームとして存続できる人数規模から始める
Q:「マーケティング活動を小さく始める」に関して、外部パートナーとは組まずに社内だけで取り組む場合、何人いれば始められるか。
庭山:当社のクライアントで言えば、最も少ないのは1人、最も多いと200人超。自社でどこまでやるかによる。外注で始めてある期間以内に内製化を目指す場合、徐々に人数を増やして組織として取り組む必要がある。担当者の急な退職、休職などもあるため、個人的には1、2人で始めるのには賛成しない。できる限りチームとして存続できる人数規模で始めるのが望ましいだろう。
梅木:私の担当企業にも、1人でマーケティングをしている会社があるが、上層部がマーケティングの重要性や実施の流れをよく理解している。明確にターゲット化した顧客の関心を得るABMであれば、3人は必要だろう。内訳は、責任を取ってくれる上層部、営業担当、マーケティング担当だ。
マーケティング担当者と営業担当者の信頼関係が生々しいコンテンツに結実
Q:ソリューションブランドを訴求するためには、象徴的な顧客事例が有効だと思うが、業界での認知度を高めるためには、技術やユースケースのアピールも重要ではないか。認知度向上とソリューションブランディングをバランス良く実施するにはどうしたらいいか。
庭山:ソリューションブランドを上げるために事例をつくる場合、顧客の実社名は出さず、架空事例として紹介するケースも多い。一方、IT(情報技術)業界の事例紹介では、社名ロゴと導入担当者の写真が入ったインタビュー形式が一般的になっている。内容については、「導入前に抱えていた課題やさまざまな事情がある中で、苦心して導入したらうまくいった」という生々しい話の方が、「ウチの会社の状況に似ているな」という共感を得やすく結果的にソリューションブランドが上がってくる。
導入前の悪い状況を取り上げるのは、広報を始めとした関係部門の調整などハードルは高いが、これらが全くないとコンテンツとしての魅力には欠けてしまう。
良いことを訴求する方法はPRにまかせ、マーケティング、デマンドジェネレーションとしては、良い評判をつくって評価してもらう必要がある。社名を出さなくてもいいので、読んだ人が「今のウチの会社のことではないか」と共感してくれて、商談をつくれるコンテンツづくりが必要だ。
だから質問の答えとしては、マーケティング、デマンドジェネレーションでのソリューションマーケティングでは、企業や製品・サービスのブランディングは意識していない、となる。
またこうしたコンテンツづくりでインタビューするのは、受注した営業担当者や導入企業であり、マーケティング担当者にはほとんど会わない。そうでないと、製品・サービス設計の裏側の話が聞けず、生々しいコンテンツがつくれない。この面でも、マーケティング担当者と営業担当者の信頼関係は非常に重要だ。
推進役を支援し、関連事例を提供
田中:弊社でも、単純に導入企業の事例紹介をすることはない。「イノベーションとカスタマーサービスでお客様の成功を支援する」というミッションの下、「どのような経営判断があってどのサービスを導入したのか」というストーリーを基に事例化することを重視している。複雑な変化が起きている現在、「なぜ経営者はデジタルトランスフォーメーションを推進しなければならないのか」をテーマにして、人にフォーカスしている。
製品・サービス導入に当たっては、必ず推進している人がいる。私たちはそうした人たちをトレイルブレイザー(登山などでの先導役)と呼んでいて、彼らを支援することを考えている。彼らはコミュニティー化もしていて、知識も蓄積している。ベンダー側にも知識があるが、顧客が自発的に必要なことを学べて、ベンダーよりも知識を持っているのがこのコミュニティーの時代だ。
そうした知識を持つ人たちをつないでいくのがコミュニティーマーケティングであり、それを支援するのがセールスフォースだ。また関連する事例をウェブ記事やホワイトペーパーに分かりやすくまとめて、お客様のフェーズに応じて提供していっている。
ツールよりもマーケティングができる人材への投資が先
Q:マーケティングオートメーション(MA)の実態を教えてほしい。
庭山:2014年から日本でもMAが販売され始めた頃から、私は将来的にMAの屍の山が築かれるだろうと予測し、寄稿記事にも書いたことがある。なぜなら、MAはあくまでもマーケティングのツールであるはずなのに、マーケティングの知識がない会社が導入しているケースが多かったからだ。MAを使うということは、デマンドセンターを運営することと同義なのに。
例えば文章で人を感動させようと思ったときに、文章修業を全く積まずに文書作成ソフトをインストールしてできる気になっているのと同じ。結局、日本ではこれまで4,000社以上がMAを導入してきたが、きちんと活用できているのは感覚的に200社程度だと思っている。まずは、ツールよりもマーケティングができる人材への投資が先だ。
田中:やはり、MAの導入をいきなりすべきではないと思う。顧客データを持っていない場合は特にそうだ。まずは顧客管理を行い、顧客へのアプローチをしっかりした上で、MAのニーズが出てきたら導入を検討すればいいのではないか。顧客とどうコミュニケーションデザインをして売り上げを伸ばしていくかという戦略をまず立てないと、成功しないだろう。私たち自身も、顧客管理から始めた企業だ。
求められるSophisticated Data
Q:デマンドジェネレーションに関する日本経済新聞社への期待は?
庭山:最近、海外からの問い合わせとして多いのは、「日本企業に対してマーケティングをかけたいのだが、どこがどんなデータを持っていて、それぞれの信頼性はどうか」ということだ。その答えは、本来的には日経だと思っている。
しかし今はそう言い切れないポイントに、データの質を語るときにsophisticated(洗練されている)かどうか、がある。企業と個人がしっかりひも付いていて、企業には業種や社員数、売り上げといった属性データが付与されている状態だ。こうしたデータが最低限の、マーケティングに使えるデータと言える。ここがまだ整備されていない日本企業も多い。今後、日経が持っているデータはもっと広く活用されるべきだと思う。
田中:これからDMP(データマネジメントプラットフォーム)の時代になっていくと、さまざまなプレイヤー同士の連携が進んでいく。そのときに、日経が持っている膨大なデータがいろんなかたちで役立つはず。
梅木:広告代理店の立場としては、リード獲得型メニューをもっと充実させてほしいと思う。北米のメディアではそうしたサービスをかなり前から提供していて、メディア側がMAに入れるためのデータの整理まで行っている。私たちはクライアントのブランディングのために新聞広告を打つこともあるが、特に外資系企業からはリード獲得など「成果に貢献する仕事をしてほしい」と厳しく言われることがある。